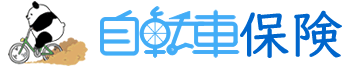高額賠償の判決がでています。
| 賠償額※ 6,779万円 |
|---|
| 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。 (東京地方裁判所 平成15年9月30日判決) |
| 賠償額※ 5,438万円 |
| 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。 (東京地方裁判所 平成19年4月11日判決) |
| 賠償額※ 5,000万円 |
| 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)女性と衝突。看護師に重大な障害(手足がしびれて歩行困難)が残った。 (横浜地方裁判所 平成17年11月25日判決) |
| 賠償額※ 4,043万円 |
| 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。 (東京地方裁判所 平成17年9月14日判決) |
| 賠償額※ 3,138万円 |
| 男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60歳)が運転する自転車と衝突。保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。 (さいたま地方裁判所 平成14年2月15日) |
具体的な
自転車事故の判例を一部紹介
(株式会社インターリスク総研まとめ)
自転車による未成年者と専業主婦の歩行者についての判例
X(事故当時68歳、女性)が交差点歩道上で信号待ちのため立ち止まっていたところ、 自転車に乗ったY1(事故当時17歳)が前方不注視により、Xの右手横に衝突した。 Xは路上に転倒し負傷した。Xは大腿骨頚部骨折の傷害を負い、後遺障害8級の障害を残した。 XはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、 709条に基づき損害賠償を請求した。裁判所はY1の責任を肯定した。 Y2・Y3は両親であることのみで具体的義務違反があるとはいえないとして責任を否定した。 Xの損害については、計約1,800万円を認容した。逸失利益については 同年齢の平均賃金から就労可能年数7年として中間利息を控除し算出し、約690万円を認容した。
平成7年1月、A(事故当時75歳、女性)が狭い道路(白色実線の外側歩道表示は有り)右側を 歩行し電柱を避けて車道に進出時、対向する無灯火の自転車に乗ったY1(事故当時14歳、中学生)が Aに衝突した。Aは頭部外傷により、後遺障害2級の障害を残した。AはY1には709条に基づき、 Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。 裁判所はY1の責任を肯定した。Y1は事故歴がなく格別、日常生活に問題行動はなかった ことなどからY2・Y3の監督責任との因果関係がないとして両親の責任を否定した。 Aの損害については、計約3,120万円(過失割合15%、既往症の減額20%適用後)を認容した。 後遺障害の逸失利益については高齢で既往症があったことなどから65歳以上女子労働者の 平均賃金の60%から就労可能年数6年として中間利息を控除し算出し、約890万円を認容した。
自転車による年金生活者の被害者の死亡事故についての判例
Y1(事故当時高校2年生、男性)は昭和60年9月、美術の校外授業で公園に来ていた。 Y1は公園の遊歩道をスポーツ用自転車で他の生徒と競争しながら疾走していた。 その際に、Y1運転の自転車はY1と同じ高校の他の生徒の写生の絵を見ていた A(65歳、男性、年金生活者)に衝突した。Aは転倒して路上に後頭部を激突させ、 8日後に病院で急性硬膜下血腫により死亡した。 Aの遺族はY1には事故回避措置不適切の過失があったとして民法709条に基づき、 Y2(公立高校、県)には監督責任があったとして国家賠償法1条に基づき、損害賠償を請求した。 裁判所は、「前方不注意、事故回避措置不適切の過失があった」としてY1の責任を肯定した。 Y2については「担当教諭が適宜巡回するなどして生徒の行動を把握し事故を未然に防止する 措置を怠った」として責任を肯定した。Aの損害については、計約2,200万円を認容した。 逸失利益については老齢厚生年金と退職年金につき平均余命を約15.5年として中間利息を控除し 算出し、約1,500万円を認容した。(ただし、将来の遺族年金相当額は妻の損害から控除)。
Y運転の自転車が信号機による交通整理の行われていない三叉路の交差点を左折した際、 対向進行してきたA(70歳、男性、年金生活者)運転の自転車と衝突した。YとAは転倒し、 Aは脳挫傷、脳内出血、急性硬膜下血腫の傷害を負った。 病院で緊急手術をしたものの植物状態に陥り、事故の1年4ヶ月後に入院したまま慢性気管支炎 を発症したことにより肺炎を併発し死亡した。Aの遺族はYに民法709条に基づき損害賠償を 請求した。裁判所はYが左折先の道路状況の注視を怠って下り勾配をかなりの速度で 反対車線方向を進行した、としてYの責任を肯定した。Aの過失についてはYの過失が重大であるのに 照らせば過失相殺すべきとは認められないとして否定した。Aの損害については、 事故と死亡の間には相当因果関係があるとし、計約3,400万円を認容した。 逸失利益については国民年金と厚生年金につき平均余命を約13年として中間利息を控除、算出し、 約1,070万円を認容した。